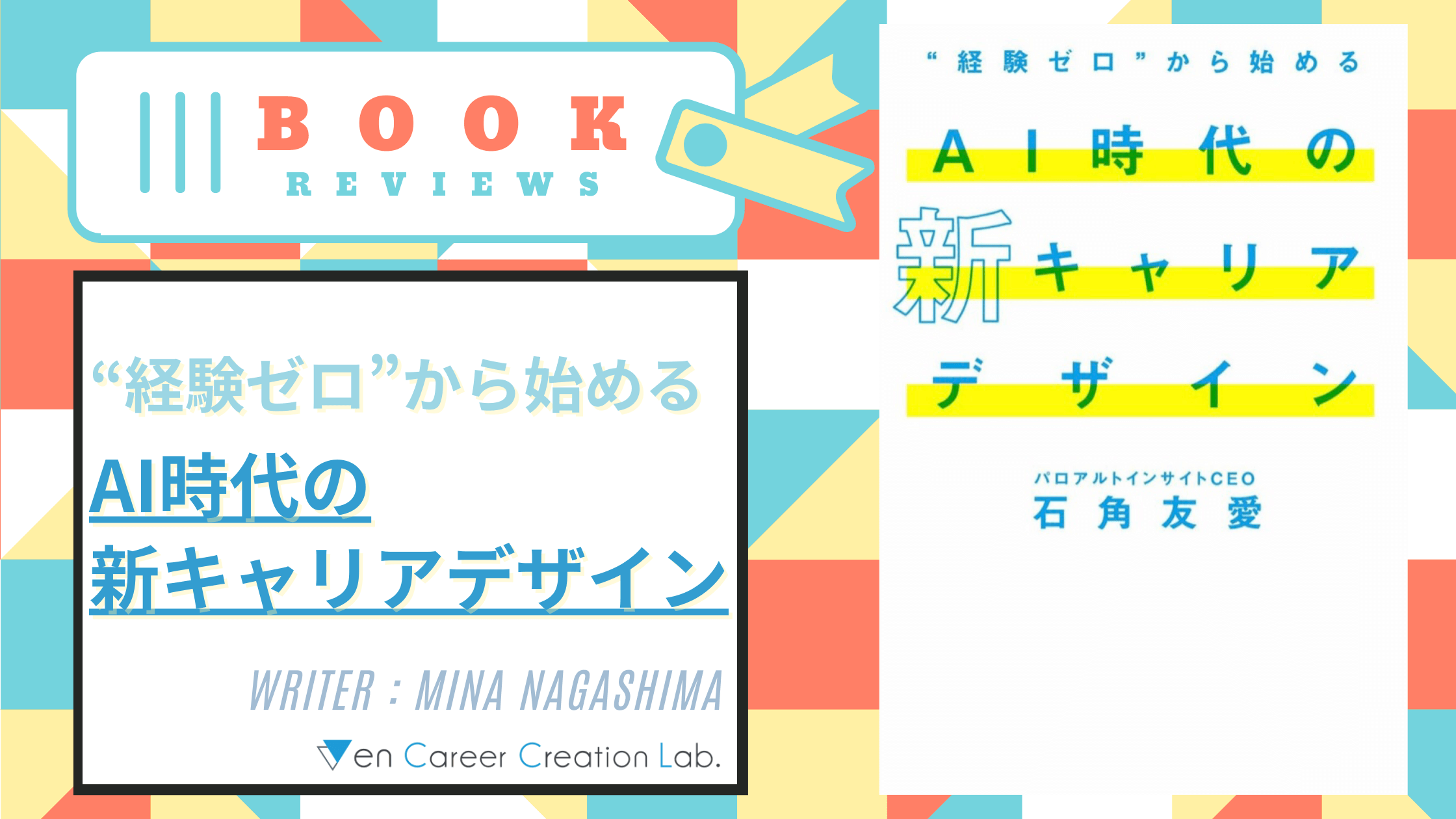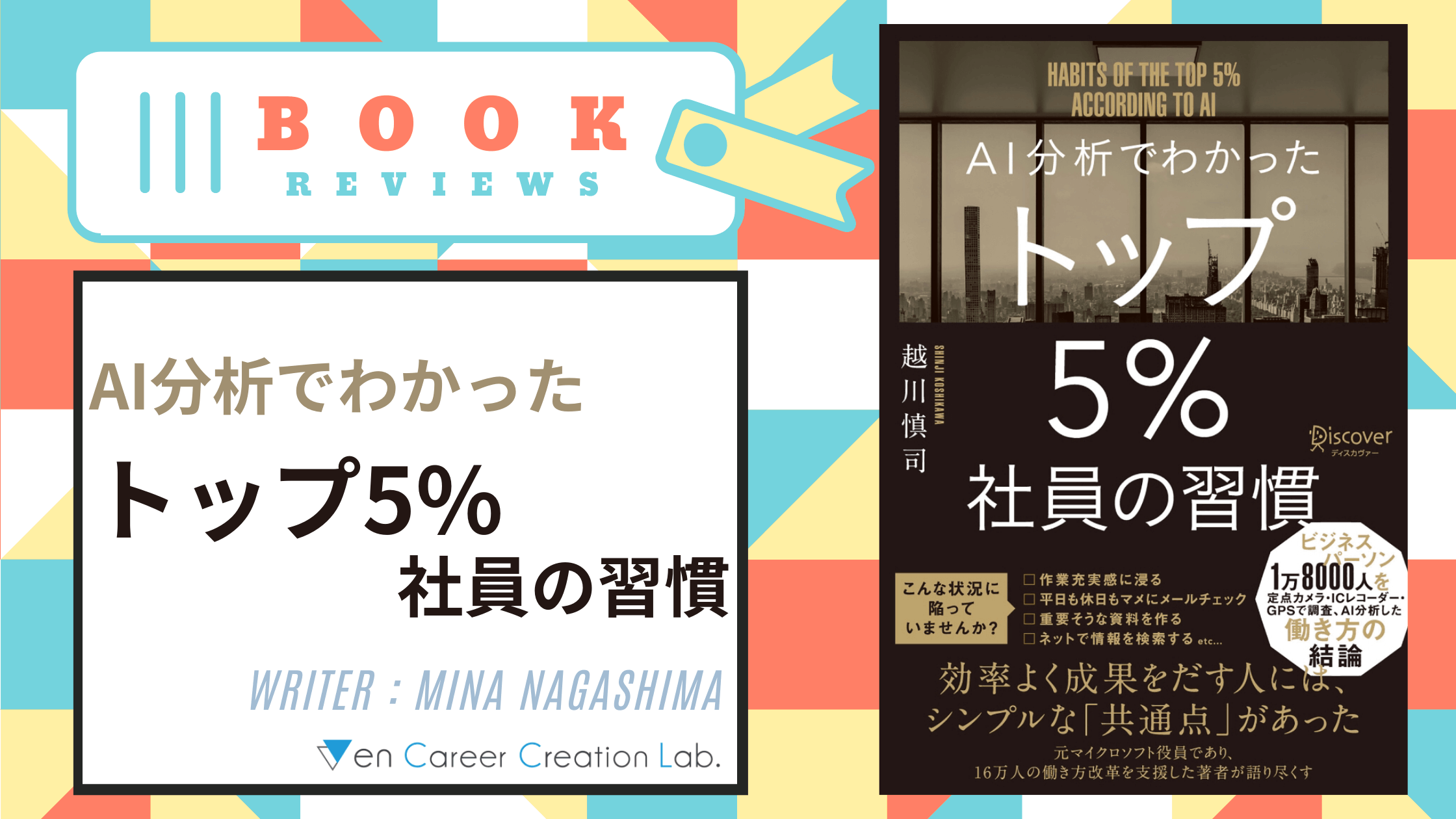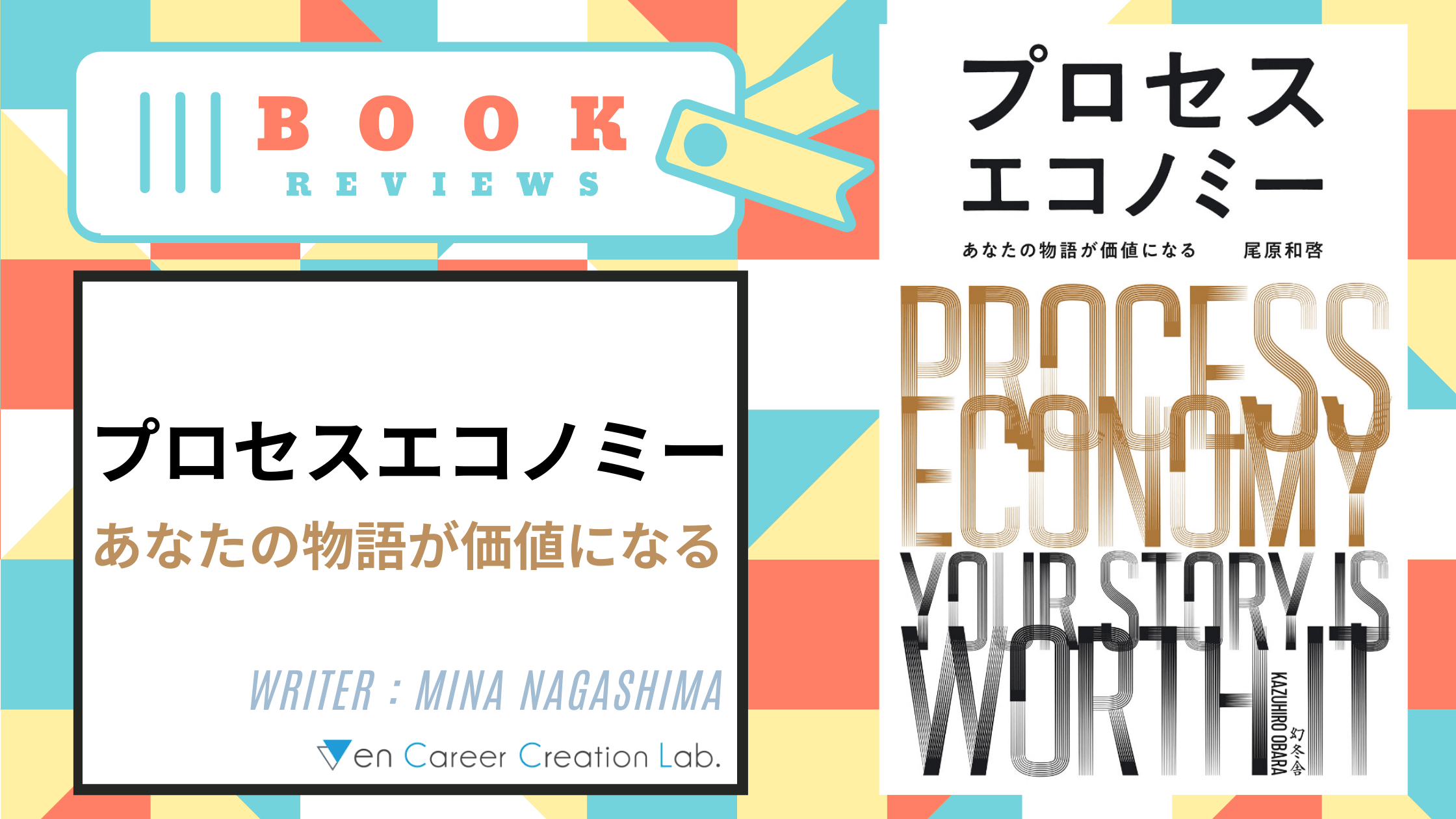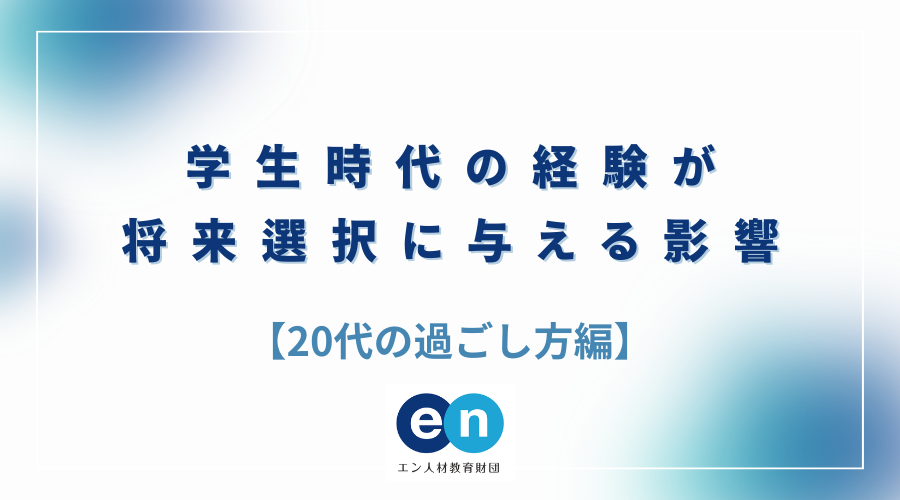11月のオススメ本『ヤバい経済学』 ―この本を読まないあなたはヤバい!?―
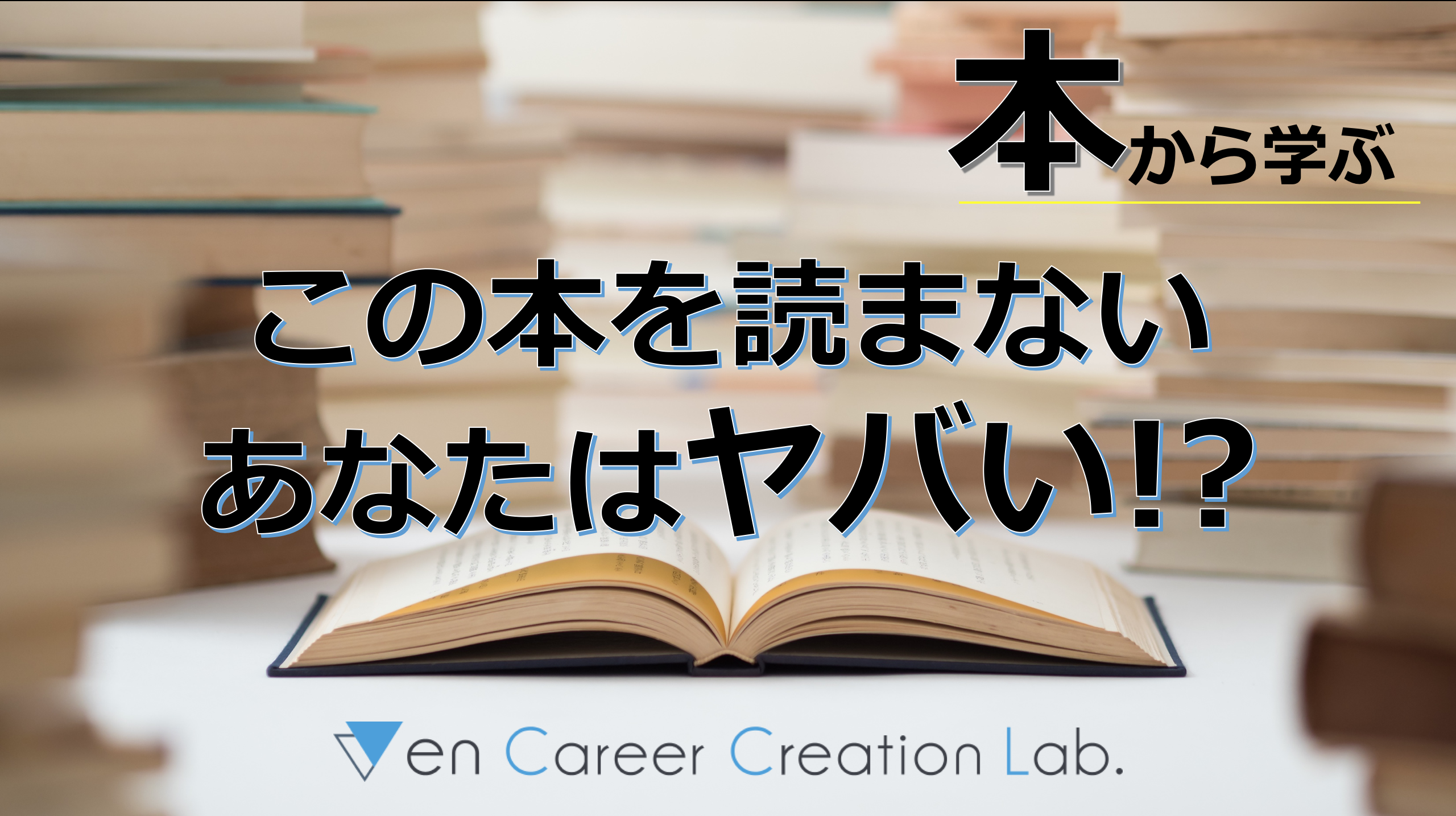
11月になりました、最近寒くなりましたよね(泣)体調に気を付けて臨んでいきたいですね!
今月もECCLオススメ本のコーナーやっていきたいと思います。
11月のオススメ本は『ヤバい経済学』です。早速レビューしたいと思います。
―目次―
本の概要
この本は世の中の経済などの裏の仕組みをちょっとブラックな事例を通して分析していくという内容です。
相撲と八百長問題、出会い系サイト、麻薬の売人、アメリカでの人種による教育格差など世間で議論されている様々な事例を分析していきます。その分析を通して社会で一般的に考えられている固定観念を疑うことで、裏の経済の仕組みを理解していく・・・という流れになっています。
自分の知らない事実にびっくりするところもありましたが、思わず「なるほど」と声に出してしまう。そんな本でした。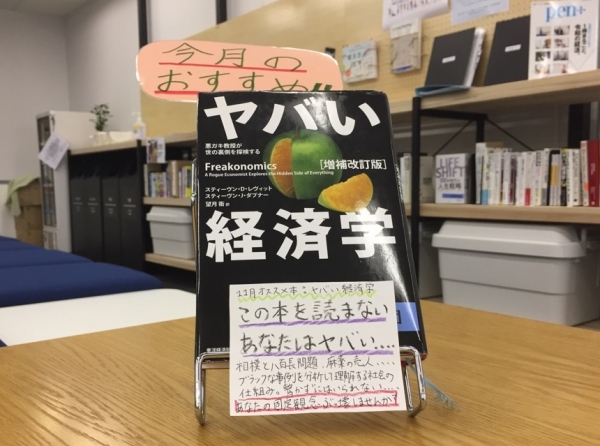
この本を読んだキッカケ
私がこの本を読もうと思ったきっかけは私がこの本を読もうと思ったきっかけは
① タイトルが面白そう
② 経済ど真ん中の本を読んだことがなかったため
③ インターンの1人が面白いと言っていたため
です。
たまにはブラックな内容の本を読んでみたいと思い手に取ってみました。普段「ポジティブ」「成長」みたいな本を読んでいる私には対照的で刺激的でした。(笑)
オススメPOINT
① 社会は様々なインセンティブから成り立っている
② 素晴らしいビジネスモデルがあってもインチキをしてしまう人もいる
③ 自分の価値観や固定観念を疑って物事を分析する大切さ
インセンティブとは、何かをすることで得られる報酬を指します。目標を達成する為の刺激ともいわれています。
この本の主張の一つが, どんなにいいビジネスモデルを作ってもインチキをしてインセンティブをもらっている人も残念ながらいるということです。そして、そういったダークな面をもつビジネスでも自分の価値観や固定観念で判断してしまう怖さを暗示しているようにも思えました。
どんなにいいサービスでも一長一短、インチキをしようとすればいくらでもインチキができます。それはビジネスの作り手だけでなく、ユーザーにとっても同様です。ユーザーも自分の知りえる情報と価値基準や固定観念から世の中のサービスや社会現象などを判断します。
しかし、そういった判断が独りよがりで自分のインセンティブだけを多く取ろうとする考えのもとであれば、どうでしょうか?その裏で気持ちよくないと思っている人もいるのかもしれませんよね。
例えば、全世界に広く展開するビジネスモデルで安価で買いやすい洗剤があったとします。CMでは「汚れがすぐ落ちる」「使いやすい」「安い」という印象を消費者に与えていますが、その洗剤の成分は水質汚染につながっています。こういう状況って気分良くならないですよね。消費者であってもサプライヤーであってもモラルを守らない言動は、迷惑行為を超えて社会問題にもなりかねないと思います。
ビジネスであっても、ユーザーであっても、固定観念にとらわれず色々な視点から検討してみる。これが重要なんだと思います。
最後に
私はこの本を読んで、ユーザーの時もビジネスパーソンの時も公正に立ち返った判断を心がけることを考えさせられました。
付加価値って言葉がありますよね。業界や会社、職種は異なっても、消費者としてサービスを利用する時でも、良い方向にも悪い方向にも自分のあり方次第で大きく変わるんじゃないかと思います。善か悪か分からない目の前にあるサービスや現象に対しても鵜呑みにせず、公正に多様な視点から考えていく自分がいれば、冷静に判断して行動することができますよね。そして、その姿勢が自分や周りの人たち、組織や社会に付加価値を与えると信じています。うん、信じたい!(笑)
この本を読んであなたの固定観念ぶっ壊しませんか?
◆編集者◆
小林航大
ECCLインターン生。趣味は読書と海外旅行。大学二年次に単身ガーナへボランティア渡航。その経験から現在大学院修士課程で国際協力や国際ボランティアについて研究中!!「とにかく世の中明るく変えたい」そんな気持ちで就職活動をしていました! よろしくお願いします!!